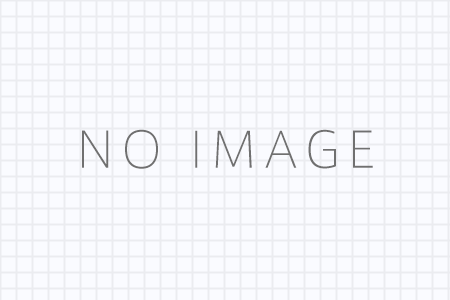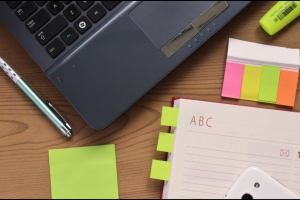2020年以降、新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い、急速に働き方が多様化しています。リモートワークやフレックス制度などで、ソーシャルディスタンスを保ちながらコミュニケーションをとったりと今までにない社内コミュニケーションが求められ流ようになりました。多様な働き方に企業側が対応しきれず、社内コミュニケーションの減少を課題としている企業も多くなってきています。
スピード感が重要視される現代のビジネスシーンにおいては、仕事上のやり取りの中心がメールからチャットに移行しつつあります。LINEなどの個人用チャットの普及で、すでに使い慣れている人がほとんどでしょう。
チャットでの社内コミュニケーションを活性化させてくれるのがビジネスチャットです。コロナ禍で急速に導入する企業が増えており、今後はビジネスの連絡手段のスタンダードになるのではと言われています。
そこで気になってくるのが、チャットでの敬語やマナーです。気軽なイメージが強いチャットですが、ビジネスのシーンでもプライベートと同じように利用できるのでしょうか。
この記事では、ビジネスチャットのルールや敬語の使い方、おすすめのビジネスチャットツールを徹底解説します。
ビジネスチャットとメールの違いは?
今までのビジネスの基本では「ビジネスの連絡手段といえばメール>電話>FAX」とされてきました。メールは情報の伝達という目的には、十分に達成出来ています。しかし、それでもビジネスチャットの普及が加速度的に進んでいるのです。なぜでしょうか?
ビジネスチャットが選ばれる理由は、メールにはない「スピード感」と「スムーズなやりとり」とされています。LINEの爆発的普及で、チャット形式がスピーディーで無駄がないことに慣れてしまいました。チャットは、電話とメールの良いとこ取りというツールなのです。
メールは送ったきりで相手が受け取ったのか、内容を確認出来たのか分かりません。確認するためには、メールを送った後に電話で確認することがビジネスの基本とされ、業務の効率化にはほど遠いものでした。しかしビジネスチャットの場合、既読の確認ができる機能があり、必要な文章のみで返事をすればいいため、業務効率化に繋がります。
”チャット”=”おしゃべり”という意味の通り、実際の会話のようにスムーズに連絡ができるので、何回もメールを送受信するよりも効率的なのです。また、ログが残っているので、過去の会話の確認も簡単です。
ビジネスチャットに「お疲れ様」は必要?
「LINE WORKS」を提供するワークスモバイルジャパンによるビジネスチャット導入企業に勤務する30代〜50代のビジネスパーソン875人を対象にして実施したアンケートで、メールなどで必ずと言ってよいほど使われる「お疲れ様です・お世話になります」などの定形挨拶について、「チャットでも必要か?」という質問の結果をご紹介します。
50代の方が30代・40代より「不要・どちらでもない」と考える傾向が強く、特に50代と30代では約2割の意識差があったのです。
具体的な数字は、「不要・どちらでもよい」と回答した50代は42.3%、30代は22.7%にとどまり、約2割のずれがありました。
結果から推測すると、役職についている方(年齢高め)の方が忙しく、チャットを使うビジネスメリットを実感している傾向にあるので、前置きの挨拶不要、簡単な報告OKという回答なのだと考えられます。
この結果から、上司が思う以上に、部下は上司に対する配慮を過度に意識している様子がうかがえました。チャットによるマナー意識のズレを無くすには、社内のチャットルールを明文化すると問題を最小化できます。
ルールがないと、部下は上司に気を使いすぎる傾向にあるのでビジネスチャットの気軽でスピーディーな面を生かしきれません。各企業内で、「挨拶不要、了解しました不要」など、統一したルールが存在すれば、余計な気を使わずにスムーズなコミュニケーションが図れるでしょう。
ビジネスチャットの口調は敬語が正解?
ビジネスチャットは、シンプルにメッセージを伝えるものですが、正しい敬語表現を用いることも大切です。ビジネスシーンにおけるチャットでは、社外でも社内でも常に敬語を使用するようにしましょう。プライベートのチャットだと使いがちな口語や言い切り表現は使わず、敬語にてビジネスの場にふさわしい表現となるよう気をつけましょう。
各企業による社風もありますが、基本的に社外はもちろん、社内において同期や部下に対しても同様です。
ビジネスチャットの内容は、仕事でトラブルが発生した際などに上司や外部などへ提出する可能性があります。常にチャット上では公的立場を考え、誰にみられても恥ずかしくないビジネスシーンを心がけることが重要です。
ビジネスチャットを有効活用するための7つのルール
多様化する働き方や便利で充実したサービスによってビジネスチャットを利用している企業が増えていますが、プライベートでも利用しているチャットだからこそ、ビジネスとしての利用ルールを決めることが重要です。情報漏えいのリスクや頻発するコミュニケーションならではのトラブルなど、企業やメンバーに損害を生んでしまう可能性もあるのです。ここでは基本的な7つのルールをご紹介します。
⒈投稿禁止事項を記しましょう
ビジネスチャットはスピーディかつ手軽さが魅力ですが、プライベートでも利用しているチャット形式だからこそ、ついつい面と向かっては言えないことやメールなど長文になると書かないことを書いてしまうメンバーが発生してしまうかもしれません。
「仕事用のツール」という事を意識して節度を持って利用することが大切です。個人間のプライベートな連絡は、「LINE」などのSNSで行うようにしましょう。
個人情報や人事情報などプライバシーに関わる内容やチームの部外秘情報などを書き込まないように徹底しましょう。
⒉正しい敬語や言葉遣いを心がけましょう
上記でもご説明しましたが、ビジネスチャットはビジネス上での会話のため上司や同僚には敬語でメッセージを送信するようにしましょう。チャットという気軽さからフラットすぎる言葉遣いは相手に不快な思いや、悪い印象を与えてしまいます。正しい言葉遣いで円滑な社内コミュニケーションを心がけることが重要です。
文字での連絡は、感情が伝わりにくく相手に高圧的な印象を与えてしまう可能性があるので、「です・ます」や「笑」「スタンプ」などを使用しましょう。社風もありますが、感情が伝わりやすくなるので状況に応じて積極的に活用していきましょう。
⒊利用時間帯を決めましょう
ビジネスチャットへの投稿、メッセージの送受信を行う時間帯をあらかじめ社内で決めておきましょう。時間制限することによって、時間外労働を減らすことができます。
ビジネスチャットのメリットに、場所や時間にとらわれず簡単にメンバーに連絡ができる、という点がありますが、業務時間外にいつでも対応をしなければいけないといった状況になることは好ましくありません。働き方改革推進の手段にもなるビジネスチャットを適正に利用するためにも利用時間を決めることが好ましいです。
⒋スタンプを利用し、挨拶は簡素化しましょう
ビジネスチャットの特徴に、メールにはないスピード感が挙げられます。「お疲れ様です。〇〇部の△△課◻◻担当の✕✕です」といったメールでよく使う定型挨拶は、最初の挨拶のみにしましょう。
また、「承知いたしました」や「かしこまりしました」「よろしくお願いいたします。」などのメッセージはスタンプでリアクションをするというルールもおすすめです。
これらの投稿が頻発されて増えることよって、最初に投稿したメッセージが見つけられない、後からメッセージを確認した人が何の件を言っているのか分からなくなり確認に時間を要することになってしまった、という事態を防ぎましょう。
⒌スレッド投稿やメンション機能を利用して返信しましょう
ビジネスチャットには、返信する相手を特定する「メンション」メッセージから個別にチャットを送信できる「スレッド」という機能があります。「メンション」機能を使用することで「送信相手を指定」する事ができるので、読み忘れを防ぐ事ができます。また複数人をメンションする事で一度にまとめて情報共有を行う事ができるので、分かりやすい情報共有のためにもぜひ利用しましょう。
⒍新規のグループやチャンネルの作成は管理職が担当しましょう
部署ごとやプロジェクトごとでチャットを分ける際には、ツール内でグループやルーム、チャンネルを作ることができますが、それらの作成作業は管理職が担当するようにしましょう。
誰でもグループを作れるようにしていると、それぞれが独自のグループを作ってしまい、グループが乱立してしまうかもしれません。管理職がグループを作ることによって、管理がしやすくなります。
⒎利用権限は必要に応じたメンバーに付与しましょう
参加メンバーには、それぞれのグループ、チャンネル内でできること、できないことを分けることができます。例えば、新規メンバーを招待ができる権限、投稿ができる権限、閲覧のみできる権限、などです。
それぞれのチーム内で適切な権限を付与することで、トラブル回避をすることが出来ます。
おすすめのビジネスチャット3サービスを徹底解説
有効活用するルールを確認したら、次はおすすめのビジネスチャット3サービスをご紹介します。全て無料トライアルがあるツールなので、ぜひ一度お試ししてみてください。
⒈誰でもすぐに使えるLINEのビジネス版「LINE WORKS」



ワークスモバイルジャパン株式会社が提供している「LINE WORK」は、チャットやスタンプはもちろん、掲示板、カレンダー、アドレス帳、アンケートなど、現場で活用できる充実したグループウェア機能を揃えたLINEのビジネス版ビジネスチャットツールです。LINEでお馴染みの使用感を踏襲しているので、どの年代の方もすぐに使いこなせる点が人気のポイントです。LINEと同じく「既読」表示機能があります。既読機能は、既読のお伺いをする必要がなく、スピーディーにやり取りができ便利です。
トークやメール、アドレス帳、ホーム(掲示板)での社内通知、メンバーの予定が把握できるカレンダー、ファイルを閲覧できるDriveなど業務の効率化に必要な機能が満載。セキュリティにおいてはユーザーの利用履歴をモニタリングできるためリスクを事前に察知し、トラブルが発生したあとの追跡も迅速に行えます。
LINEであればつかえるという学生インターンや20代の社員が多いカジュアルな企業におすすめです。
セキュリティレベルは、日本の法令はもちろん国際規格を遵守し、国際認証を取得した高いレベルの情報管理システムでサービスを管理しています。LINE WORKSのデータは、全てセキュリティ専門のエンジニアチームによる24時間365日の体制でモニタリングしているので安心です。
【料金プラン】
スタンダード 450円/ユーザー/月(年間契約)
アドバンスト 800円/ユーザー/月(年間契約)
※フリー(はじめてビジネスチャットを利用する会社が無料で100人まで利用できるプラン)
LINE WORKSサービスサイト : https://line.worksmobile.com/jp/
⒉入力中の表示でスムーズにやり取り可能なパイオニア「Slack」



Slack Technologies, Incが提供する「Slack」は、日本はもちろん、世界的にも広く認知されているビジネスチャットのパイオニアです。世界150ヵ国以上で利用されているだけでなく、有料プランの利用企業数も16万9,000社以上と多くの国と企業で利用されています。
定型的なアクションやコミュニケーションを自動化してSlackワークスペースのワークフローに変換できるツールが「ワークフロービルダー」です。業務に必要なメンバーを探し出す時間が短縮でき、情報を適切な担当チームへ自動で収集して受け渡すことが可能です。
他社の既読機能とは違い、「〇〇さんが入力しています」と表示する機能があり、相手の対応状況をリアルタイムで把握できるようになっています。チャットは、迅速な情報交換ができるために短いメッセージが相手とのやりとりで交差しがちですが、この機能の「入力中」の表示があれば、相手の返答を待ってから返信でき、スムーズに会話を進められるため人気があります。
【Slackの価格】
プロ:850円/ユーザー/月
ビジネスプラス:1600円/ユーザー/月
Enterprise Grid :要問合せ
※無料プラン有
Slackサービスサイト : https://slack.com/intl/ja-jp/
⒊仕事を完遂させるオールインワン・コラボレーションツール「Tocaro」



伊藤忠テクノソリューションズ株式会社が提供する「Tocaro(トカロ)」は、組織で働くビジネスマンがより効率的に働くことをサポートすることを目的として自社開発したビジネスチャットツールです。仕事に必要なあらゆる情報を、簡単かつ安全に共有するための様々な機能が満載で、業務の依頼や仕様変更など重要な連絡を見える化して、業務の抜け漏れや遅れを防ぎます。
金融レベルの高セキュリティが人気の秘訣で、IPアドレス制限・モバイル端末制限・機能制限・ユーザー権限など、多くのセキュリティ機能を組み合わせることで、あらゆるセキュリティ問題・社内ルールの壁を乗り越えて、利便性を損なわずに安全なコミュニケーション環境を構築します。また、世界中で数十万社が利用するセキュアなファイルストレージサービスBox®︎と強度な連携ができる唯一のツールです。
『プロジェクト管理』『リアルタイムチャット』『ワークボード』の3つの特徴的な機能を始め、『ワークフロー』『ファイル共有』『既読管理』『ビデオ通話』『検索』『API・連携機能』『アクセス管理』『専用アプリケーション』などを装備しています。
【料金プラン】
スタンダードプラン 800円/ユーザー/月
ビジネスプラン1,000円/ユーザー/月
エンタープライズプラン 要相談
※無料トライアルあり
Tocaroサービスサイト:https://tocaro.im/
ルールを守って正しくビジネスチャットを活用しましょう
ビジネスチャットは、円滑にコミュニケーションを行うために、迅速で簡潔な返信を行うことが大切なだと思われがちですが、「早く返信を返さなければいけない」や「敬語をきっちりしなければ」などのように囚われてしまうと、業務に支障が出てしまったり相手と距離をとり過ぎてしまうことになるので賢く利用しましょう。
またビジネスチャットの暗黙のビジネスルールを知らないことで信頼関係に傷がついてしまったりトラブルが発生してしまう事があります。導入前にしっかり社内でルールを決めて周知させ、臨機応変に対応することが重要です。