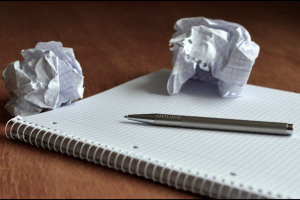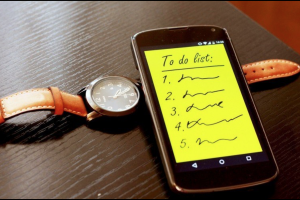新型コロナウイルスの影響で急速に進んだ「働き方改革」は、「リモートワーク」や「在宅勤務」など私たちの働き方を変えただけでなく、業務で使うシステムやサービスの見直しや改善にまで進んできています。
各種システムやツールのSaaS化は急速に進んでいます。例えば、リモートワークで重要となるWeb会議やチャットツールは、SaaSで提供されるものが中心となっています。
こうした見直しや効率化は、ヘルプデスク分野にも浸透し始めています。長らく横ばいだった企業のデジタル化が、ツールを活用し、IT革新に取り組む中で急激に発展していることは喜ばしいことです。
しかし、一方であまりに急激に変化したため、インフラを支える情報システム部門(ヘルプデスク業務)には大きな負担がかかってしまっています。社内での問い合わせ業務が、対面中心たっだのがオンライン中心へとシフトしています。
業務をスムーズに進めるためにも、SaaS活用を前提としたサポート、ヘルプ体制の再構築を考えてみましょう。この記事では、SaaSとSaaSで提供されるヘルプデスクツールについて徹底解説します。
「SaaS」とは?
SaaSとは、「Software as a Service」の頭文字を取った略語で「サース」と読みます。「サービスとしてのソフトウェア」を意味します。これまでパッケージ製品として提供されていたソフトウェアを、インターネット経由でサービスとして提供・利用する形態のことを指します。パソコンにソフトウェアをインストールする必要がないのです。
主な特徴は、こちらです。
・データをインターネット上に保存することができる
・PC、スマートフォン、タブレットなど端末を選ばずにデータにアクセスできる
・複数の人間が同一データを共有し、更に編集もできる
「PaaS」「IaaS」との違いは?
よく混合されがちですが、クラウドサービスに分類されるSaaSとIaaSとPaaSですが、それぞれが提供するサービスは似ているようで少し異なります。
大まかにご説明すると、ネットワークや仮想サーバーといった開発に必要なインフラのみを提供するのがIaaSだとすれば、開発ツールやデータベースといった開発環境(プラットフォーム)までカバーするのがPaaSです。
IaaS、PaaS、SaaSの区別についてまとめると、ソフトウェアサービスを提供するのに必要な構成要素の提供段階によって区別することができます。その構成要素は大きく分けて、ネットワーク、ハードウェア、オペレーティングシステム(OS)、ミドルウェア、アプリケーション、の5つに区分されます。
基本的にはこの5つはこの逆順に依存関係にあります。3つの各構成要素は下記の通りです。
「IaaS」→ネットワーク、ハードウェア、オペレーティングシステム(OS)
「PaaS」→ネットワーク、ハードウェア、オペレーティングシステム(OS)、ミドルウェア
「PaaS」→ネットワーク、ハードウェア、オペレーティングシステム(OS)、ミドルウェア、アプリケーション
SaaSは、5つの要素がすべて含まれており、近年最も利用されているクラウドサービスとなりました。
「SaaS」を導入するメリットとは?
ここからは、SaaSを導入するメリットについて徹底解説します。
メリット1)手軽にサービスを導入できる
SaaSは、サービス提供会社が用意したサーバーやアプリケーション、データベースなどのシステムを、複数のユーザーで使用するため、ある程度できあがった環境が最初から整っています。そのため、サーバーを自社で用意するなどの手間が少なく、素早く、簡単に利用を開始することができます。
メリット2)場所を選ばずにアクセスできる
インターネットに接続できる環境や端末があれば、場所を選ばずにサービスにアクセスが可能です。ソフトウェアはアカウントごとに提供されているため、オフィスだけではなく、自宅や外出先からもアクセスすることができます。そのため、出張先、テレワークや在宅勤務でも問題なく利用することが可能です。
メリット3)デバイスが違ってもサービスを利用できる
専用のアカウントを作り、インターネットからアクセスして、SaaSのソフトウェアの機能を使うため、インターネット環境さえあれば、デバイス(パソコン・タブレット・スマートフォンなど)が違ってもアカウントが同じであれば、同じサービスを利用することができます。例えば、社内ではPC、外出先ではタブレット、自宅ではスマホなど、場所に応じたデバイスの使い分けに対応しているのでとても便利です。
メリット4)コストを抑えてサービスを導入できる
インターネット環境さえあればOKなので、利用するための環境構築が不要なため、導入費用を抑えることができます。また、月額制で使った分の料金だけの支払いとなるため、メンテナンス費用などが別途発生しません。コストが限られている企業にとってはSaaSを利用することで費用負担を抑えながらスムーズな事業運営を目指すことが可能です。
メリット5)複数人で同時に作業できる
サービス提供会社によっては、編集機能や管理機能がついているものがあり、複数のユーザーによって同時に管理することや編集作業をすることができます。誰かが作成したドキュメントを、他の誰かが編集して管理することもでき、複数人でファイルを共有して管理編集することも可能です。
メリット6)運用負担がとても少ない
サービス提供者側が勝手にアップデートしてくれるのでソフトウェアの更新の手間がかからず、いつでも最新の状態の機能を使用できます。そのため、メンテナンス専門人員やシステムエンジニアなどを専任にすることなく、ソフトウェアの管理に手間がかからないため、コストも抑えられます。
SaaS型のあるヘルプデスクツール3選
SaaS型のあるヘルプデスクツールのおすすめ3選をご紹介します。
1. OrangeOne株式会社「Freshservice」



《特徴》
OrangeOne株式会社提供の「Freshservice」は、クラウド・SaaS型の社内向けITSMツールであり、即日運用も可能な簡単設定で問い合わせ体制を改善できます。
インシデント管理、問い合わせ管理、ナレッジ管理、CRM・FAQなど、基本的な機能は全て網羅しています。複数のチャネルに対応しているため、さまざまな方法で問題を報告できます。
利便性の高いリクエスト管理と承認の自動化により、効率の良い運用が可能です。リモート環境での導入にも対応しており、ヘルプデスク担当者の負担軽減にもつながります。
《料金》
25,200円 ~ 144,000円(年間一括契約)
2. 株式会社クレオ「SmartStageサービスデスク」
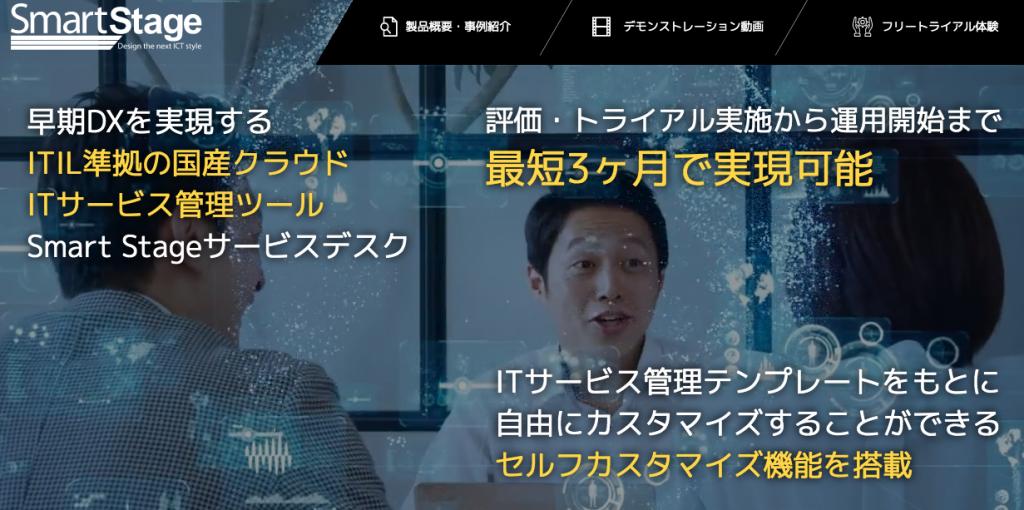
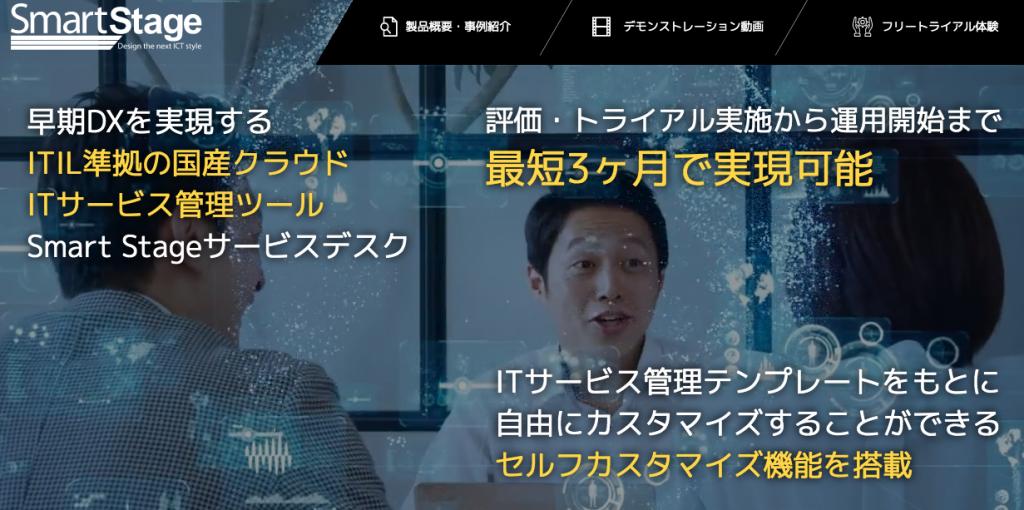
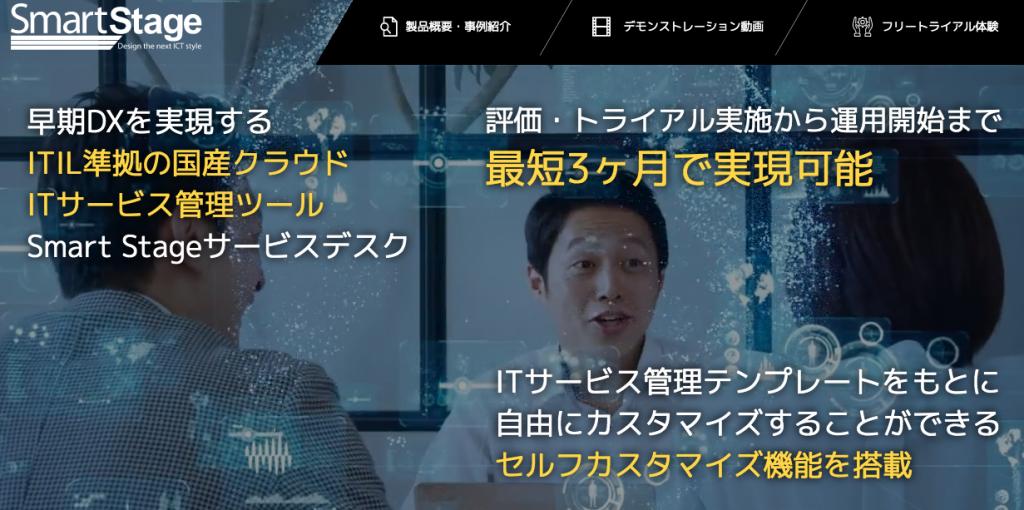
《特徴》
株式会社クレオが提供する「SmartStageサービスデスク」は、ITIL(ITサービス管理における成功事例文献)に準拠したシステム運用体制を整えられるツールです。
ITILを積極的に取り入れ、業務のベストプラクティスをテンプレートで導入しているため、ヘルプデスクの社内問い合わせの体制を見直したい企業におすすめです。
ノンプログラミングで設定できるため、自社の問題にも柔軟に対応しています。インシデント管理、問合せ管理、エスカレーション、技術者手配、ナレッジ管理など、基本的な機能は充実しています。
3. 株式会社野村総合研究所「Senju/SM」



《特徴》
「Senju/SM」は、ITIL(ITサービス管理における成功事例文献)で求められるITシステムの運用プロセスを実現するツールです。
株式会社野村総合研究所の運用現場から生まれたサービスデスクツールであり、日本ならではの精緻な運用や特別要件に対しても柔軟な対応が可能なとことが人気です。
国内シェアNo.1の実績があるため、豊富なナレッジ(知識)やノウハウを活かし、システム導入後も定着・継続的改善など手厚いサポートを提供するとことが特徴です。
インシデント管理、問合せ管理、エスカレーション、技術者手配、ナレッジ管理、CRM・FAQなどの基本的な機能はもちろんカバーしています。
手軽に導入できるSaaS型のヘルプデスクを検討してみましょう
いかがでしたでしょうか?会社のイントラをイチから構築する大かがりなクラウド型よりも、手軽にすぐに導入でき、運用負担が少ないSaaS型は、メリットがたくさんあります。
ヘルプデスク業務をスムーズに進めるためにも、SaaS活用を前提としたサポート、ヘルプ体制の再構築を考えてみましょう。
【関連記事】
社内ヘルプデスク業務を効率化するオールインワンチャットツール「Tocaro」