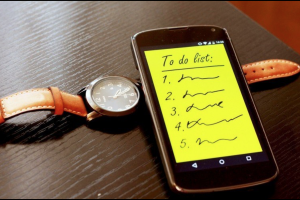あなたはビジネスチャットを「単なる連絡手段」として運用し、その真のポテンシャルを引き出せていますか?
ビジネスチャットへの投資は、生産性の「最大化」、情報の「迅速化」、そして組織の「透明化」を実現するための重要な戦略です。しかし、その鍵を握るのが「言葉遣い」です。
カジュアルすぎるチャット文化は、時に重大なコンプライアンスリスクや無用なコミュニケーションコストを生み出し、かえって効率を低下させているのが実情です。「どの敬語を使えばいいか」「どこまで略していいか」といった現場の迷いが、企業全体のスピードを鈍らせています。
この記事は、チャットによる言葉遣いのトラブルを防ぎ、企業の信頼性を高めながら、真の効率化を実現するルール策定の具体的な手法と、場面別の模範例文を徹底解説します。さらに、ルール運用を強力にサポートする「おすすめビジネスチャット5選」もご紹介します。
企業が言葉遣いのルールを定めるべき3つの理由
ビジネスチャットにおける言葉遣いの問題は、個人のマナーや慣習に委ねるべきではありません。経営層・管理職がガイドラインを策定し、組織的に取り組むべきリスクマネジメントと生産性向上に直結する課題です。ここでは、その3つの核心的な理由を解説します。
1. 誤解を生みやすいテキストコミュニケーションの特性
対面や電話と違い、チャットでは声のトーンや表情、ジェスチャーといった非言語情報が一切伝わりません。
「承知しました」と「了解です」の違いは明確ですが、「承知」だけ、「りょ」だけといった極端な省略形は、受け取り側によっては「ぞんざいな対応」と捉えられ、無用な人間関係の摩擦を生みます。特に、忙しいときほど文面が短くなりがちであり、意図しない誤解や軋轢が生まれるリスクが高まります。
2. 企業文化の形成とガバナンス強化
チャットの言葉遣いは、その企業の文化を映し出します。カジュアルな言葉遣いが許容されるスタートアップ文化と、厳格な礼節を重んじる老舗企業では、求められるレベルが異なります。
ルールを明確化し、チャット上でも適切な「ビジネスチャット 言葉遣い」を徹底することは、統一されたプロフェッショナリズムを組織全体に浸透させ、ガバナンスを強化する土台となります。
3. ハラスメント・リスクの回避
チャットのやり取りは「記録」として残ります。何気ない一言や、絵文字、スタンプの不適切な使用が、後からパワーハラスメント、セクシャルハラスメントと指摘されるリスクを常に内包しています。
特に、深夜・休日・休暇中の連絡は「時間」のハラスメントと見なされる可能性があり、言葉遣いと同時に利用時間や緊急度に関するルールも合わせて定める必要があります。
ビジネスチャットの「3つの基本ルール」
「効率化」と「丁寧さ」を両立させるためには、「どこまで省略を許すか」という明確な境界線(ガイドライン)を設定することが、情報システム部や経営企画室の重要なミッションとなります。
【ルール1】レスポンス速度と緊急度の定義
チャットの最大の敵は「通知疲れ」です。全てのメッセージに即レスポンスを求めていると、従業員は常にチャットに張り付くことになり、集中力を削がれます。
| 緊急度 | 目的とするレスポンス時間 | 適切な対応方法とルール |
| 高(即時対応) | 5分以内 | 電話・直接対話を推奨。チャットで送る場合は**【緊急】【要電話】**などの目印を文頭につける。 |
| 中(早めの対応) | 1時間以内 | 最優先で対応。内容を確認したら「🙏」や「確認しました」のスタンプ/絵文字で**既読・一次返信**を行う。 |
| 低(時間があるとき) | 1日以内 | 業務のキリが良いタイミングで確認。通知をオフにしても良いグループである旨を明記する。 |
重要: 夜間・休日のチャット利用は原則禁止とし、高緊急度の場合のみ電話で連絡するルールを徹底します。
【ルール2】敬語の「省略可否」ラインの設定
「簡潔さ」と「失礼にあたらないこと」のバランスを取るためのルールです。
| 敬意の対象 | 推奨される言葉遣い | 許容される省略形(社内限定) | 原則禁止の言葉遣い |
| 社外・取引先 | 丁寧語(~です、~ます)必須。 | なし | 「りょ」「おけ」「マジで」「わら(笑)」 |
| 社内(目上/他部署) | 丁寧語推奨。依頼時は「〜していただけますか」などクッション言葉を使用。 | 「承知です」「了解です」「対応します」 | 「りょ」「おけ」「〜してください」 |
| 社内(同僚/部下) | 丁寧語を基本とし、指示は明確に。 | 「確認しました」「OK」「承知」 | 感情的な表現、命令口調 |
特に「りょ(了解)」は、親しい間柄でも人によっては不快に感じるため、社内でも原則禁止とする企業が増えています。「承知しました」「承知です」を推奨しましょう。
【ルール3】絵文字・スタンプの使用基準
感情を伝えやすくする絵文字やスタンプですが、これも言葉遣いの一部として管理が必要です。
- 承認・リアクション用途に限定する: 既読、承諾、感謝(例: 「👍」「✅」「ありがとうございます」スタンプ)など、テキスト入力の手間を省く目的のみで許可します。
- 感情的なスタンプは禁止: 怒り、悲しみ、過度な喜びを示すキャラクターものは誤解の元となるため禁止します。
- 社外とのやり取りでは原則使用禁止: 相手から使用された場合でも、極力テキストで返信することを推奨します。
【場面別】失敗しないビジネスチャットの言葉遣いと例文集
ここからは、具体的なシチュエーションで使える「ビジネスチャット 言葉遣い」の例文をご紹介します。全てに共通するのは「結論ファースト」と「次に何をしてほしいか(依頼事項)の明確化」です。
1. 上司・取引先への報告・相談(丁寧さと簡潔さ)
| シーン | NG例文 | 推奨例文(ポイント) |
| 依頼・お願い | 〇〇さんの件、急ぎで資料ほしいです。 | 【依頼】〇〇プロジェクトの資料作成をお願いできますでしょうか。 締切は〇日中、必要な情報はこのスレッドで共有します。お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします。(依頼内容と締切を明記) |
| 進捗報告 | 〇〇、遅れててやばいです。もう少し時間ください。 | 【進捗報告】〇〇の件、遅延しており大変申し訳ございません。 現在、A工程で技術的な問題が発生しており、解決に〇時間程度必要です。〇時までに進捗を再報告いたします。(状況と次の報告時刻を明確化) |
| 確認依頼 | これってどうするんでしたっけ? | 【〇〇の件ご確認をお願いします】 〇〇の仕様について、A案とB案で迷っています。過去の事例ではB案が多いですが、今回の目的を考慮するとA案も検討すべきでしょうか。ご判断をお願いします。(選択肢を提示し、判断を促す) |
| 決定事項 | 社長からOK出たので進めます。 | 【決定事項】〇〇の件、承認されました。 社長より最終承認をいただきましたので、本日よりプロジェクトをキックオフします。関連資料を添付いたしますので、各自ご確認ください。(誰が承認したかを明確にし、次の行動を指示) |
2. 部下・メンバーへの指示・依頼(配慮と明確さ)
部下へのチャットでは、効率化のためにカジュアルになる傾向がありますが、「命令口調」や「突き放した言い方」はハラスメントに繋がりかねません。依頼と感謝をセットにすることが重要です。
| シーン | NG例文 | 推奨例文(ポイント) |
| 指示・依頼 | 〇〇、この資料今日中に作っといて。 | 〇〇さん、【ご協力のお願い】 大変恐縮ですが、こちらの資料を本日中に作成いただけますでしょうか。(依頼形) 急ぎで申し訳ありませんが、ご対応いただけると助かります。(クッション言葉と感謝) |
| フィードバック | このやり方はダメ。もう一度考え直して。 | 〇〇さん、資料拝見しました。ありがとうございます。 一点、より良くするための提案ですが、こちらの〇〇のデータについて、別の角度からも分析を加えてみてはいかがでしょうか? (感謝と改善提案をセットで) |
| 簡単な承認 | おけ | 承知しました。進めてください。 / OKです。 (「おけ」ではなく「OK」や「承知」を使う) |
| 労い | お疲れ様 | 〇〇さん、お疲れ様です。対応ありがとうございます! その後の進捗はどうですか? / 昨日のご対応、助かりました。(労いの言葉に感謝を加える) |
3. 返信(リアクション)の仕方(簡潔なリアクションとクッション言葉)
チャットでは、「既読」が相手に伝わらない場合(特にグループチャット)があります。相手の時間を奪わないよう、簡潔かつ確実に伝わる言葉遣いを心がけます。
| シーン | NG例文 | 推奨例文(ポイント) |
| 承諾・同意 | わかった。 | 承知しました。 / 了解です。(社内) / 確認いたしました。 |
| 質問への回答 | はい。 | はい、その認識で合っています。 / はい、〇〇についてはご指摘の通りです。 |
| 検討が必要 | 無理。今忙しい。 | ありがとうございます。**恐れ入りますが、**現在別件対応中のため、〇時までに確認し、あらためてご連絡させていただきます。(クッション言葉と返信時刻の明記) |
| 感謝 | ども | ありがとうございます! / 大変助かりました。(感謝を省略しない) |
ルールを「形骸化」させない!現場で定着させるための3つのステップ
ルールを策定しても、現場の慣習や忙しさに流されてしまっては意味がありません。特にスピード感が求められるチャットにおいて、新しい「言葉遣い」のルールを従業員に浸透させ、習慣化させることは、経営層や管理職にとって最も難しい課題の一つです。このセクションでは、策定したガイドラインを日常業務に落とし込み、「形骸化」を防ぐための実践的な定着化ステップを解説します。
ステップ1:トライアル部門を設定し、段階的に適用する
全社一斉に新しいルールを導入すると、現場に混乱や反発を生む可能性があります。ルールを定着させるには、特定の部門でスモールスタートを切ることが重要です。
- 先行導入部門の選定: 経営企画室、情報システム部、または特にチャットの利用頻度が高いプロジェクトチームなど、比較的ルールを浸透させやすい部門を対象に設定します。
- 「チェックリスト」の試用: この先行部門で、作成した言葉遣いのチェックリストや例文集を実際に使用してもらい、「使いやすさ」「現場での疑問点」を収集します。
- 成功事例の可視化: トライアル期間中に「生産性が上がった」「誤解が減った」といった具体的な成功事例をデータと共にまとめ、全社に共有することで、本格導入への納得感を高めます。
ステップ2:管理職による「模範的な行動」と「ポジティブフィードバック」
ルールが定着するかどうかは、管理職の行動にかかっています。トップダウンでの強制ではなく、リーダーシップによる習慣化を促します。
- 管理職向け研修の実施: 管理職に対し、一般社員よりも厳しいレベルでルール遵守を徹底する研修を行います。特に、部下に対する指示出しや、夜間・休日の連絡を避ける時間管理の重要性を強調します。
- 「見守り」と「称賛」の文化: 不適切な言葉遣いを見つけた際に、頭ごなしに注意するのではなく、適切な言葉遣いをした従業員を積極的にチャット内で称賛するポジティブフィードバックを推奨します。心理的安全性を確保しつつ、望ましい行動を促します。
- 定期的な運用会議: 各部門の管理職が集まり、チャットの運用状況や言葉遣いに関する課題を共有する会議を定期的に開催し、ルールの微調整や全社展開の計画を練ります。
ステップ3:「言葉遣いチェックリスト」の作成と継続的な教育
ルールを忘れないよう、日々の業務で常に参照できる環境を整備します。
- クイックリファレンス(虎の巻)の作成: 複雑なガイドラインから、「りょ、禁止」「依頼は【依頼】から開始」といった、チャットルームにピン留めできる数項目のチェックリストを作成します。
- 自動リマインドの活用: チャットツールの通知機能やリマインダー機能を使い、週に一度など定期的に「言葉遣いガイドライン」をチャンネルに自動投稿し、意識の薄れを防ぎます。
- オンボーディングへの組み込み: 新入社員や中途入社者向けのオリエンテーションに「ビジネスチャットマナー研修」を必須項目として組み込み、入社直後から正しい文化を習得させます。
言葉遣いの課題を機能で解決するビジネスチャット5選
言葉遣いの問題は、マニュアルだけでは解決しません。組織のガバナンス強化とコミュニケーション効率の向上には、それをサポートする「ツール」の力が必要です。特に、タスク連携やシンプルな操作性で、自然と適切な言葉遣いとプロセスを習慣化させる機能を持つチャットを選ぶことが、導入成功の鍵となります。ここでは、先に述べた言葉遣いの課題解決に役立つおすすめのツールを5つご紹介します。
1. Tocaro(トカロ)



Tocaroは、シンプルなインターフェースで国産ならではの使いやすさに定評があるビジネスチャットです。国産で使いやすいシンプル設計。タスク管理・ファイル共有機能が充実しており、日本の商習慣にフィットしやすい。
おすすめポイント
- タスク管理機能との連携による会話の明確化: Tocaroはチャット機能とタスク・プロジェクト管理機能が連携しています。会話の中で「依頼」「承認」「完了」といったタスクを明確に切り分けられるため、「これは単なる相談か?それともタスクなのか?」といった言葉遣い(意図)の曖昧さが解消され、コミュニケーションロスを防ぎます。
- ファイル管理に強い: 報告・相談の際に必要なファイルをチャットに紐づけて一元管理できるため、「どのファイルの、どの部分について話しているのか」という文脈を明確に保てます。
- シンプルなUIでルールを浸透させやすい: 多機能すぎて複雑になりがちな海外製ツールと比べ、シンプルな設計で誰でも直感的に使えるため、先に述べた言葉遣いや利用時間のルールを組織全体にスムーズに浸透させやすい特長があります。
公式サイト:https://tocaro.im/
2. Slack(スラック)



世界的に利用されているチャットツールです。豊富な外部連携とカスタマイズ性が魅力です。外部連携機能(App)が豊富。高いカスタマイズ性とオープンなコミュニケーション文化を促進。
おすすめポイント
- リアクション機能の充実: 絵文字リアクションの種類が豊富で、テキストを入力しなくても「確認しました」「OK」といった意図を瞬時に伝えることができ、チャットの効率化に貢献します(前述の「ルール3」に基づき、使用するリアクションを限定しましょう)。
- スレッド機能による会話の整理: 複雑な議論や複数のトピックが混在するチャンネルでも、スレッド機能を使うことで、特定の話題に関する言葉遣いや情報を一つにまとめて整理できます。
公式サイト:https://slack.com/intl/ja-jp/
3. Microsoft Teams(マイクロソフト チームズ)



Microsoft 365ユーザーにとっては、その他のOffice製品とシームレスに連携できることが最大のメリットです。Microsoft 365とのシームレスな連携。Web会議、ファイル共有、チャットを統合。
おすすめポイント
- Teams会議と連携した文脈の維持: チャットで議論した内容からそのままビデオ会議へ移行できるため、チャットの言葉遣いだけでは伝えきれない微妙なニュアンスや感情を、即座に対面コミュニケーションに切り替えて補完できます。
- 高度なコンプライアンス・セキュリティ機能: 情報システム部が重視するログ管理やセキュリティ、監査機能が充実しており、不適切な言葉遣い、情報漏洩のリスクを組織全体で管理しやすい環境を提供します。
公式:https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-teams/
4. Chatwork(チャットワーク)
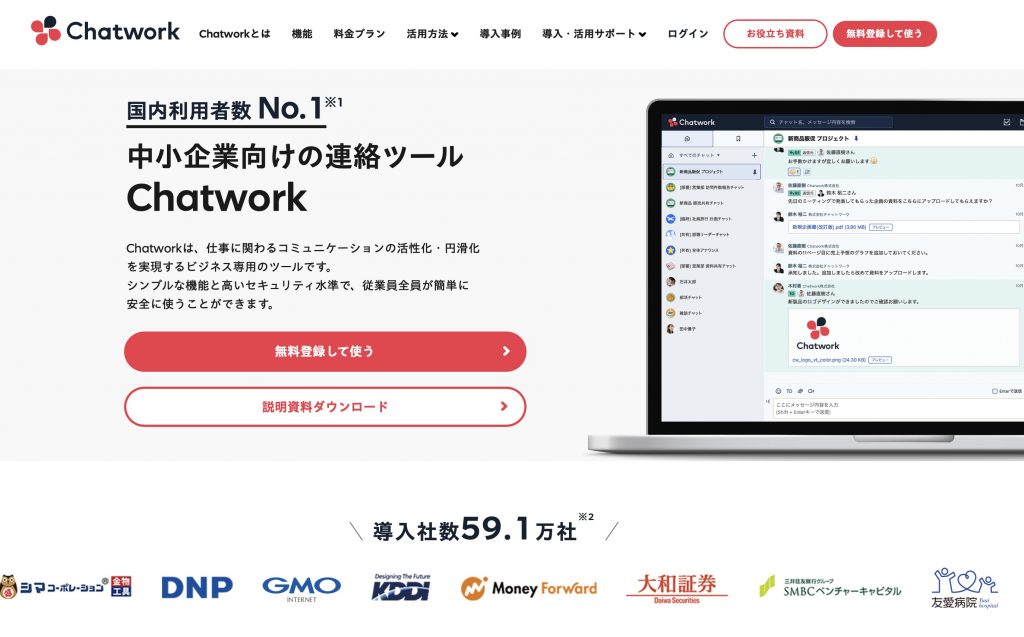
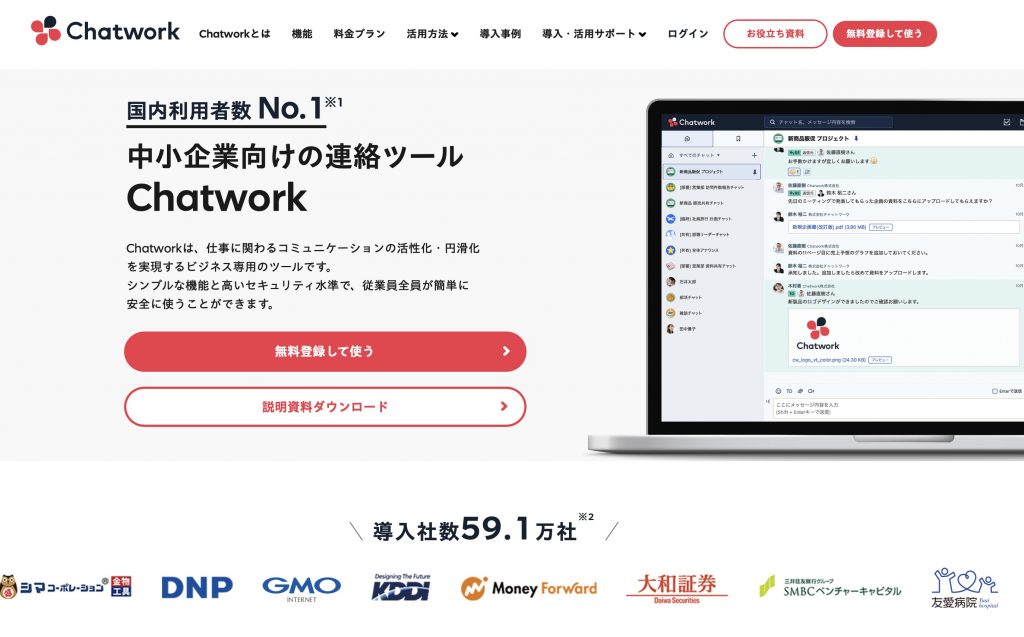
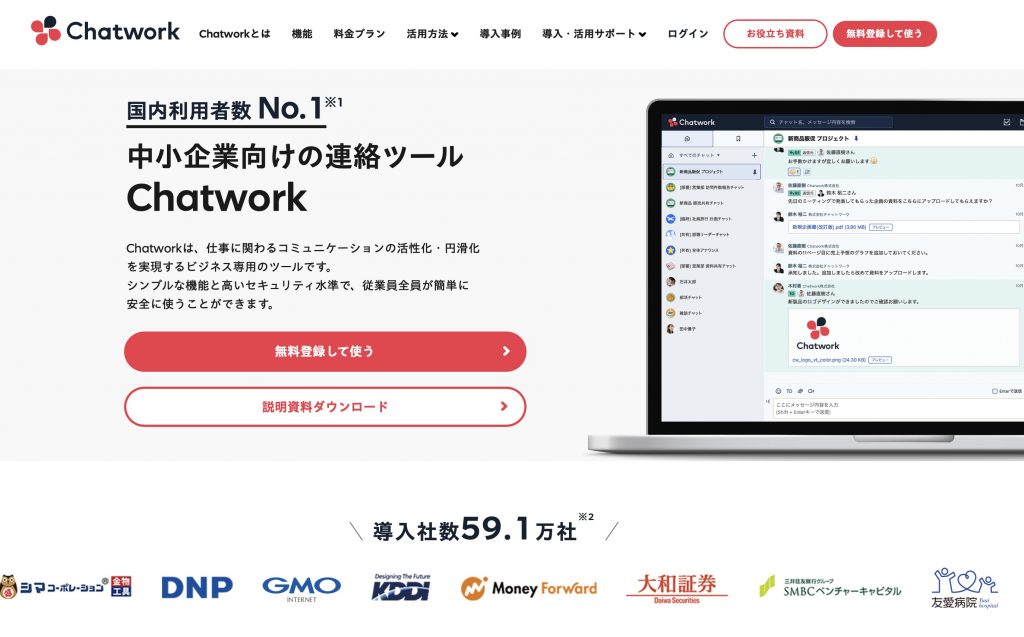
Chatworkは、日本企業での利用実績が非常に多く、特に中小企業や非IT企業にも浸透しています。国内トップクラスの導入実績。シンプルで直感的な操作性。タスク管理機能が強力。
おすすめポイント
- タスク管理機能の分かりやすさ: メッセージからワンクリックでタスクを作成できるため、「これは単なる報告か、タスクか」というコミュニケーション上の曖昧さをなくし、言葉遣いの意図を明確にします。
- シンプルでメールに近いUI: 従来のビジネスメールに近い感覚で使えるため、チャット初心者やITリテラシーが高くないメンバーでも抵抗感が少なく、ルール(言葉遣いマナー)を浸透させやすいのが特長です。
公式サイト:https://go.chatwork.com/
5. LINE WORKS(ラインワークス)



普段使いの「LINE」と酷似した操作性を持つビジネスチャットです。LINEとほぼ同じ操作感で導入容易。カレンダーやアンケート機能なども搭載。
おすすめポイント
- 既読機能: LINEと同じく「既読」機能があるため、相手にメッセージが届いているか、確認したかどうかを瞬時に判断できます。「見たなら返信しろ」というプレッシャーにならないよう、「既読=確認。返信は不要」という社内ルールを徹底することが、言葉遣いの効率化に繋がります。
- 直感的なUIで導入障壁が低い: 従業員の多くがLINEの操作に慣れているため、ツールの操作方法に関する教育コストが極めて低く、すぐにガイドライン(言葉遣いルール)の周知と運用に集中できます。
公式サイト:https://line.worksmobile.com/jp/
導入・運用時に注意すべき点
ビジネスチャットの言葉遣いを組織に定着させるには、ルール策定後の運用と監査が不可欠です。以下の点に留意してください。
1. 利用ガイドラインの策定と周知徹底
先に述べた「3つの基本ルール」を含めたガイドラインを正式な社内文書として策定し、全従業員に必須の研修を実施してください。
ガイドラインに必ず含めるべき項目:
- 緊急連絡の定義と手段: (チャットは低・中、電話は高など)
- 禁止されている省略形・絵文字: (「りょ」や不適切なスタンプなど)
- 夜間・休日の連絡ルール: (原則禁止、やむを得ない場合の具体的な方法)
- チャットの公的な記録としての認識: (「軽い会話」ではなく、「証拠」として残ることを強調)
2. ログの管理と監査体制
言葉遣いのトラブルやハラスメントが発生した場合、ログが唯一の証拠となります。
- データ保持期間の設定: 企業のコンプライアンス方針に基づき、ログの保持期間を明確に定め、確実に記録・保管されるように設定します。
- 監査権限の設定: 特定の権限を持つ管理者(情報システム部や法務部)のみがログを閲覧できる体制を構築し、透明性とプライバシー保護を両立させます。
3. 定期的な研修・教育の実施
一度ルールを決めても、時間の経過とともに従業員の意識は低下します。
- 定期的なeラーニング: 毎年または四半期に一度、「ビジネスチャット 言葉遣いとハラスメント防止」に関するeラーニングを実施します。
- 新しいメンバーへのオリエンテーション: 新入社員や中途入社者に対しては、入社時の必須研修としてチャットマナーを徹底的に教え込みます。
ビジネスチャットの言葉遣いは効率と信頼の要
ビジネスチャットの「言葉遣い」は、単なるビジネスマナーの問題ではなく、企業の生産性、従業員エンゲージメント、そしてコンプライアンスを左右する重要な経営課題です。
曖昧な慣習に任せるのではなく、明確なガイドラインを策定し、そのルールを補強するようなツール(特にタスク管理連携やシンプルなUIを持つTocaroなどの国産ツール)を賢く活用することが成功の鍵となります。
「簡潔さ」と「丁寧さ」のバランスを最適化し、全社的にルールの浸透を図ることで、貴社のビジネスチャットは、真の生産性向上ツールへと進化するでしょう。