ビジネスチャットツールを比較したいと思っているあなたは、おそらく新規導入の検討(どのツールが自社の業務形態や規模に合っているのか判断がつかない)、既存ツールの課題(今使っているチャットツールの機能が不足している、あるいは社員に定着していないため、より適切なツールへの乗り換えを検討したい)、そしてDX推進(コミュニケーション基盤を強化し、意思決定のスピードアップと生産性の向上を図りたい)といった、いずれかの課題に直面していることでしょう。
ビジネスチャットは単なる「会話の道具」ではありません。情報共有、タスク管理、ファイル連携など、業務全体の生産性を左右する重要なインフラです。ツール選定で後悔を避けるためには、各ツールの強みと弱みを正確に把握し、自社のニーズに合った比較軸を持つことが不可欠です。
この記事では、ビジネスチャットを比較する際の5つの重要な評価軸を提示し、特に機能面で強みを持つおすすめツール5選を徹底解説します。この記事を読めば、貴社が自信を持って最適なツールを選定するための明確な道筋が見つかるはずです。
後悔を避けるためのビジネスチャット比較5つの評価軸
多機能なビジネスチャットの中から最適な一つを選ぶには、ただ単に機能一覧を眺めるだけでは不十分です。以下の5つの視点から、自社の現状と将来の展望を照らし合わせて比較を行いましょう。
比較軸1:コア機能と拡張性(連携性)
ビジネスチャットの基本機能(チャット、ファイル共有、グループ作成)はどのツールでも備わっていますが、連携性が将来の生産性を大きく左右します。
- 統合型 vs 連携特化型:
- 統合型(例:Teams, LINE WORKS):最初からWeb会議、カレンダー、タスク管理など必要な機能が一式揃っているため、他のツールを増やす手間が少ない。
- 連携特化型(例:Slack):外部の2400以上のサービス(SaaS)と連携できるため、既に利用している既存の業務システム(CRM、SFA、人事管理など)とチャットを連動させたい場合に強い。
- APIの柔軟性: 自社開発のシステムやニッチな業務アプリとの連携が必要な場合、API(外部連携機能)の公開度や柔軟性も重要な比較ポイントです。
比較軸2:タスク管理・フローティング機能
「メッセージをいかに流さずタスク化できるか」は、組織の返信漏れや業務停止を防ぐ生命線です。
- タスク化の容易さ: メッセージをワンクリックでタスクに変換できるか、それとも手動でコピー&ペーストが必要か。
- リマインダー機能: 特定のメッセージを指定した日時に通知できるリマインダー機能が充実しているか。
- プロジェクト管理機能との統合: 単なるToDoリストではなく、プロジェクトボードなどより高度な管理機能が組み込まれているか。
比較軸3:定着率・使いやすさ(UI/UX)
どんなに高機能なツールでも、社員が使わなければ意味がありません。特にデジタルリテラシーに差がある組織では、UI/UXが定着率を左右します。
- 学習コストの低さ: 新しいツールを導入する際、社員がマニュアルなしで直感的に使えるか。
- モバイル対応: 外出先やリモートワーク環境で、PC版と同じ機能と操作性を維持しているか。
- 国産か海外製か: 画面の日本語表示やサポート体制が、日本のビジネス慣習に合っているかどうかも確認しましょう。
比較軸4:セキュリティと管理機能
企業規模が大きくなるほど、セキュリティと管理の容易さは必須要件となります。
- 認証・認可: シングルサインオン(SSO)に対応しているか、二段階認証の設定が可能か。
- ログ・監査: 監査に必要なログが取得できるか、利用状況を管理画面から詳細に把握できるか。
- データ保管場所: データを国内サーバーに保管しているかなど、コンプライアンス上の要件を満たしているか。
比較軸5:料金体系と費用対効果
料金体系はツールによって大きく異なります。「無料プランで十分か」「有料プランの機能が本当に必要か」を検討しましょう。
- 無料版の制限: 参加人数、メッセージ履歴の検索期間、外部連携機能などに制限がないか。
- 月額費用: ユーザーあたりの月額費用と、必要な機能が揃っているプランの価格を確認します。特に大規模組織の場合、ランニングコストが重要な比較軸となります。
おすすめビジネスチャットツール 5選の徹底比較
上記の比較軸を踏まえ、現在、日本国内で特に支持され、それぞれが異なる強みを持つビジネスチャットツールを5つご紹介します。
1. Tocaro(トカロ):タスクと情報を一元管理したい組織に最適



Tocaroは、ビジネスチャット、タスク管理、ファイル共有を融合させた国産のオールインワン型ツールです。メッセージからタスクを即座に作成・管理できる点が最大の特徴であり、単なるチャットツールを超えたプロジェクトマネジメントツールとして活用できます。
Tocaroの注目すべきポイントは、「情報のフロー」と「業務のストック」を分断させない仕組みにあります。一般的なチャットツールが抱える「会話が流れて、やることが埋もれる」という課題を根本から解決するため、他の多くのツールと比較して、特に返信漏れ防止と進捗管理の容易さで優位性があります。
また、国産サービスであるため、日本語サポート体制も充実しており、日本の商習慣に合わせたきめ細やかな機能改善が期待できます。
公式サイト:https://www.tocaro.im/
2. Chatwork(チャットワーク):シンプルな操作性とタスク管理を重視する組織に
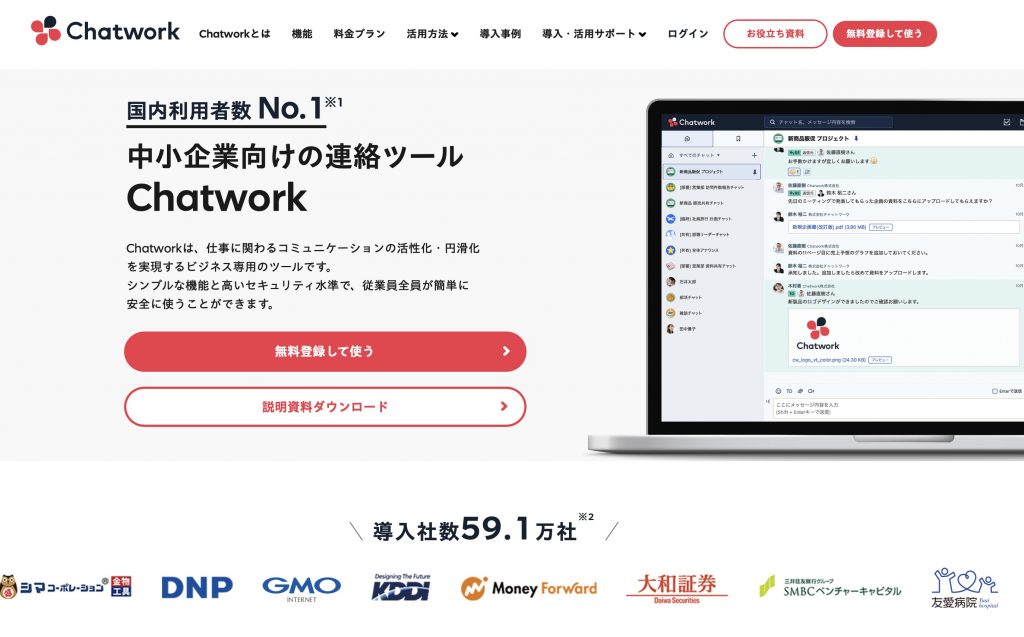
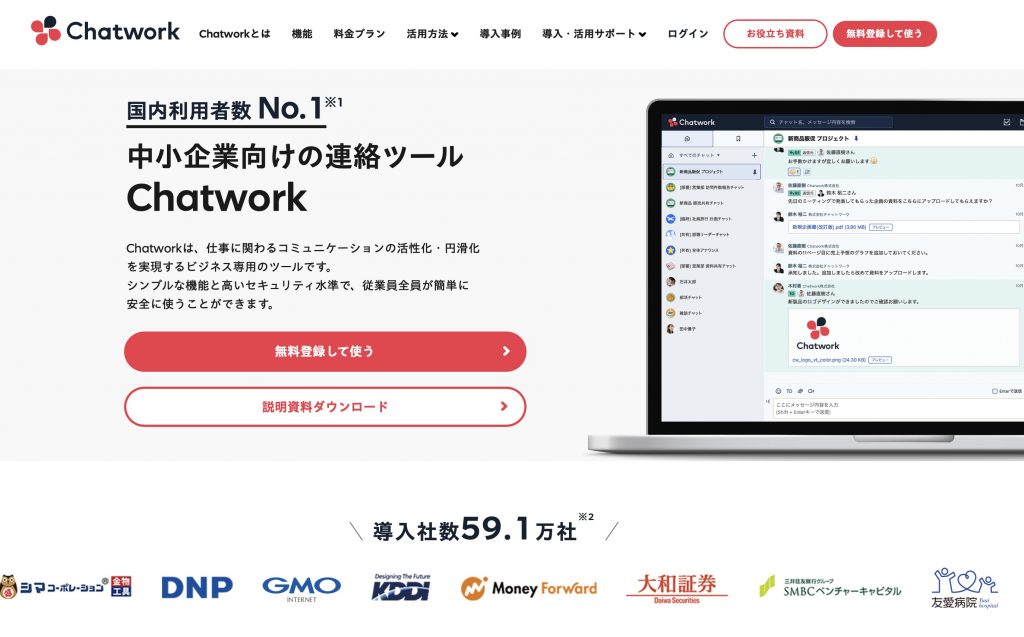
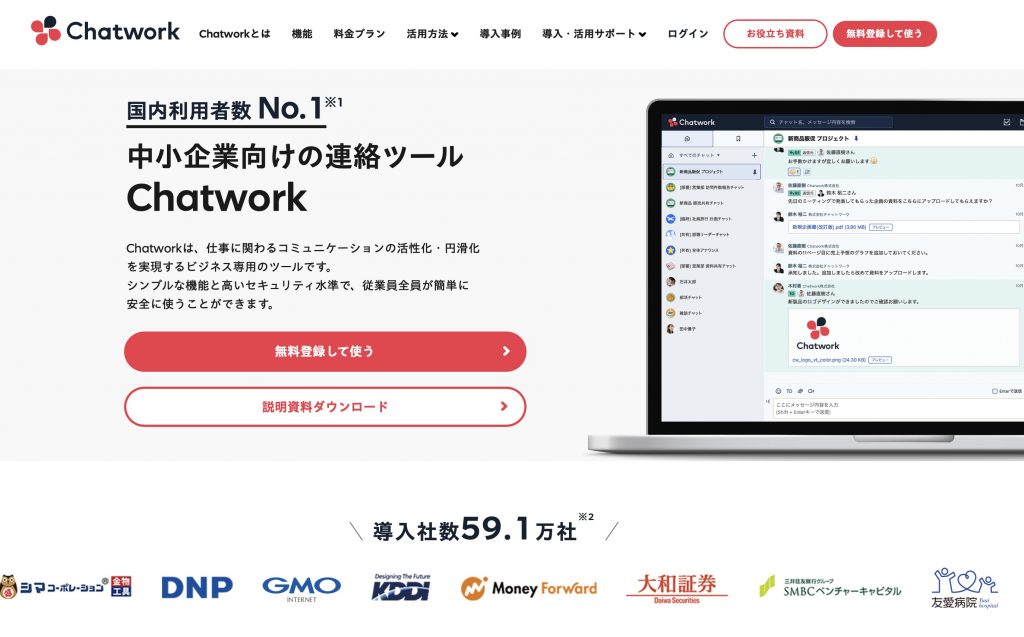
Chatworkは、日本の中小企業を中心に広く利用されている国産のビジネスチャットです。UI/UXが極めてシンプルで、パソコン操作に不慣れな方でも直感的に使える点が大きな強みです。
メッセージと並行して画面右側にタスク管理機能が標準で搭載されており、チャット内容を忘れることなくToDoリストに組み込めます。多機能性よりも「シンプルさ」「タスク管理のしやすさ」「導入の容易さ」を比較軸とする組織には最適な選択肢です。
公式サイト:https://go.chatwork.com/ja/
3. Slack(スラック):外部連携と拡張性を最大限に追求したい組織に



Slackは、世界的に利用されているグローバルスタンダードなビジネスチャットです。最大の特徴は、その圧倒的な外部連携機能と拡張性にあります。営業管理(Salesforce)、人事管理(SmartHR)、開発管理(GitHub)など、既に利用している 2400以上の外部サービスをSlackに統合できます。
高度なワークフロービルダー機能を使えば、定型業務(報告、申請など)を自動化できるため、ITリテラシーが高く、既存の業務システムをチャット中心に統合したい組織にとっては最高の選択肢となります。
公式サイト:https://slack.com/intl/ja-jp/
4. Microsoft Teams(マイクロソフト チームズ):Microsoft 365の利用を前提とする組織に



Microsoft Teamsは、Microsoft 365(旧Office 365)のサブスクリプションに含まれる統合コミュニケーションプラットフォームです。Word、Excel、PowerPoint、OneDrive、SharePointなど、Microsoft製品との連携は他の追随を許しません。
Web会議機能が強力で、チャットからすぐに会議を立ち上げられるシームレスさが魅力です。既にMicrosoft 365を導入している企業、またはメール、ファイル共有、Web会議を一つのプラットフォームに集約したい企業にとって、最も費用対効果が高く、導入しやすいツールです。
公式サイト:https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-teams/
5. LINE WORKS(ラインワークス):全社員への高い定着率を最優先する組織に



LINE WORKSは、コンシューマー向け「LINE」とほぼ同じインターフェースを持つビジネスチャットです。多くの社員が既にLINEの操作に慣れているため、教育コストがほぼゼロで、全社への定着率を最速で高められる点が最大の強みです。
既読機能がグループチャットでも「誰が読んだか」を明確に表示するため、確認責任を明確化したい組織に適しています。また、カレンダー、掲示板、ドライブなど、ビジネス利用に必要なグループウェア機能も統合されています。
公式サイト:https://line.worksmobile.com/jp/
自社に最適なビジネスチャットツールを選ぶ 3つのステップ
複数のツールを比較した上で、貴社に最適な1つを選ぶために、以下の3つのステップで最終決定を行いましょう。
⒈優先順位の確定
まずは、先に挙げた5つの比較軸の中から、自社にとっての優先順位1位と2 位を明確に決定します。
- | 貴社の課題/ニーズ | 優先すべき比較軸 |
- | 「返事がない」問題を解消したい | タスク管理・フローティング機能、定着率 |
- | 既存のSaaSと連携したい | コア機能と拡張性(APIの柔軟性) |
- | とにかく全社員に使ってほしい | 定着率・使いやすさ(UI/UX) |
- | 費用を抑えたい | 料金体系と費用対効果 |
- | Office製品をフル活用したい | コア機能と拡張性(TeamsのMicrosoft連携) |
⒉無料トライアルによる「定着テスト」の実施
候補を2〜3つに絞り込んだら、無料プランやトライアル期間を利用して、現場でのテスト利用を実施します。特に、現場の社員に「使いやすさ」についてヒアリングを行うことが重要です。
- 利用する部署のITリテラシーが平均的か、高いか、低いか
- 最も利用頻度の高い機能(メンション、タスク作成など)がスムーズに操作できるか
この段階で、最も定着率が高そうだと判断されたツールが、貴社にとっての「正解」である可能性が高いです。
⒊セキュリティ・管理体制の最終確認
最終候補が決まったら、情報システム部門のチェックリストに沿って、管理者権限、監査ログ、データ保管場所、SSO対応など、見落としがちな管理・セキュリティ要件を再確認します。これにより、導入後の予期せぬトラブルを防ぎます。
導入後の定着が鍵!後悔を避けるためのチェンジマネジメント戦略
最適なツールを選び終えた後、多くの企業が直面するのが「定着しない」という問題です。ビジネスチャットの導入は「システム入れ替え」ではなく、「コミュニケーション文化の変革」を伴います。後悔を避けるためには、以下のチェンジマネジメント戦略が不可欠です。
1. 専任チームの設置と段階的なロードマップ策定
ツール導入の責任を情報システム部門だけに負わせず、現場の代表者も含めた「利用推進チーム」を編成します。このチームが中心となり、全社一斉導入ではなく、部署やプロジェクト単位での小規模なテスト導入から始め、段階的に利用範囲を広げるロードマップを策定します。初期の成功体験を積み重ねることが、全社展開時の抵抗感を減らす鍵となります。
2. ツールエバンジェリスト(伝道師)の育成
新しいツールへの抵抗感を和らげるには、現場のロールモデルが必要です。各部署からITリテラシーが高く、新しいコミュニケーションに意欲的な社員を「エバンジェリスト(伝道師)」として選任し、先行してツールを徹底活用してもらいます。彼らが日常業務で便利な使い方を発信したり、ちょっとした疑問に答えたりすることで、ボトムアップでの利用促進と学習コストの軽減に貢献します。
3. 目的別・階層別トレーニングの実施とフィードバックの収集
ツールの全機能を網羅するトレーニングは非効率です。「一般社員向け(基本操作と利用ルール)」「管理者向け(セキュリティ・ログ管理)」「プロジェクトリーダー向け(タスク・進捗管理)」など、階層と目的に合わせたトレーニングを実施します。また、運用開始後 1ヶ月、 3ヶ月のタイミングで必ずアンケートを実施し、「使ってみて不便な点はないか」「ルールは守られているか」といった現場の生の声(フィードバック)を収集し、初期設定や運用ルールを柔軟に改善していく姿勢が定着につながります。
5つの軸と定着戦略で貴社に最適なインフラを
ビジネスチャットの比較・選定は、貴社の将来の生産性を決める重要な投資です。「多機能だから」「有名だから」といった理由だけで選ぶのではなく、「タスク管理のしやすさ」「既存システムとの連携性」「社員の定着率」という3点に特に注目して比較検討を進めてください。
そして、選定後は「チェンジマネジメント戦略」に基づき、利用ルールとサポート体制を盤石にすることで、初めてツールの真価が発揮されます。
この記事でご紹介した5つの評価軸、おすすめツール、そして3つの定着戦略が、貴社のコミュニケーションインフラ強化に役立つことを願っています。























