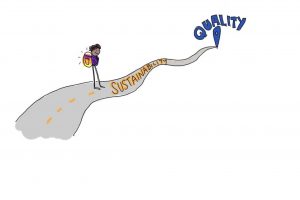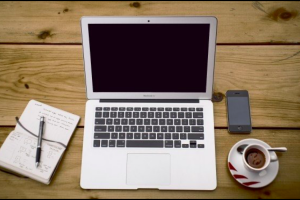生産性向上は、少子高齢化が進行し、働き手が減ることが予測される日本の企業にとって最も重要な経営課題の一つだと言えます。
各社生産性向上に向けた施策は打ち出し、実行はしているものと、実行した施策がどのような成果を出しているか?そしてどのように管理をすればよいか?という点においてはまだ成果を見いだせていない企業も多いと見受けられます。
今回は、生産性向上をどのような指標で分析・管理するかと具体的な改善施策をご紹介していきたいと思います。
そもそも「生産性」とは何か?
生産性とは、投入した経営資源(ヒト・モノ・カネ)に対してどれだけ成果を出せたかを計る指標です。これを把握することで自社の効率性や付加価値をどの程度生み出したかを把握することが出来ます。
生産性は、成果を投入した経営資源で割ることで求めることができ、この数値が高くなればなるほど少ないインプット(資源)で大きなアウトプット(成果)が出せたと判断することが出来ます。
生産性を分析する際に活用する具体的な指標
生産性を分析する際には3つの指標がよく使われます。それが「労働生産性」「付加価値」「労働分配率」の3指標です。
1. 労働生産性
「労働生産性」は、従業員一人ひとりの労働力に対してどのくらいの成果が出たかを計る指標です。
実際に出た売上高、利益、生産量などの成果を従業員数などの労働力で割ることで算出し、この指標が高くなればなるほど少ない労働力で大きな成果が出せたこととなります。
労働生産性を上げるためには、成果を増やすか労働力を減らすかのどちらかに対して対策を打つ形となります。
2. 付加価値
付加価値とは、仕入れてきた資源に対して追加された企業独自の新しい価値を計る指標です。
付加価値の算出方法は中小企業庁方式と日銀方式の2つの方法があり、一般的には中小企業庁方式の控除法が使われています。
【中小企業庁方式(控除法)】
付加価値=売上高-外部購入価値(材料費、運送費、外注費など)
【日銀方式(加算式)】
付加価値=経常利益+人件費+賃借料+減価償却費+金融費用+租税公課
3. 労働分配率
労働分配率は、人件費が企業が生み出した付加価値のどの程度の割合を占めるか把握する指標です。人件費には給与・賞与のほか福利厚生費や退職金なども含まれます。
労働分配率は、『(人件費÷付加価値)×100』で求められ、中小企業の場合、5-60%が平均値となっています。
生産性向上のための具体施策
日本においては、人口減少などもあり、今後これまで以上の生産性向上が求められます。ここでは生産性向上を実施する際に効果的な施策を3つご紹介します。
1. 業務の見える化
まず実施したいのが、「業務の見える化」です。
社員一人ひとりがどのような業務をどのようなフローで行っているかを可視化することにより、課題の発見がスムーズにできるようになります。また、この可視化の過程で、各個人が自分自身の業務内容や業務フローを見直す機会にもなり、生産性向上の一助となります。
2. 業務の標準化
次に検討したいのが、社内で実施している「業務の標準化」です。
会社全体で業務のマニュアル化やルール化を行い標準化することで、成果の品質に差が出るのを防いだり、退職や異動の引き継ぎによる混乱の削減など、企業としての品質維持と効率化の実現が可能となります。
3. 業務の自動化
「見える化」「標準化」が出来たら次は「業務の自動化」を検討します。
これまで社員が行っていた業務をシステムやロボットなどの導入によって自動化し、生産性向上を狙います。業務によっては人間が行うよりもミスの発生率を低下させられる上に業務時間の削減も見込まれます。
生産性向上はこれからの企業の重要テーマ
生産性向上の分析・管理方法と具体的な改善策をご紹介してきましたが、いかがだったでしょうか?
冒頭でもお伝えしたように、企業にとって生産性向上は大変重要なテーマとなります。今回ご紹介したような指標を明確に定め、分析管理を徹底することで、飛躍的な生産性向上を目指してください。